菖蒲色(しょうぶいろ)は、落ち着いた青紫系の色合いを持ち、日本の伝統色の一つとして親しまれています。本記事では、絵の具を使って菖蒲色を作る方法について詳しく解説します。
菖蒲色を作るための色の組み合わせ
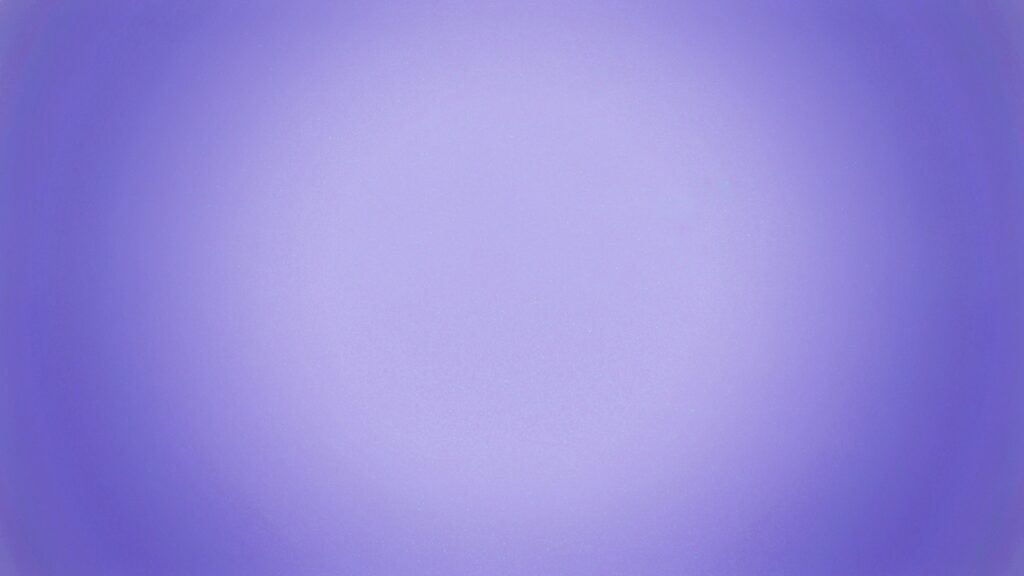
菖蒲色を作るためには、基本となる色の組み合わせを理解することが重要です。ここでは、青紫、赤、黄色を使った方法について解説します。
青紫と黄色の混色
菖蒲色を作る基本的な方法は、青紫に少量の黄色を加えることです。黄色を加えることで、色味を調整しながら望ましい色に近づけます。
ただし、黄色を入れすぎると色がくすんだり、緑がかってしまうことがあるため、少量ずつ加えながら調整することが大切です。
また、絵の具の種類によって発色が異なるため、異なるメーカーの青紫や黄色を試して、自分に合った色の組み合わせを見つけるのもよいでしょう。
赤と黄色を混ぜた際の効果
赤と黄色を混ぜるとオレンジ系の色になりますが、これを青紫に加えることで、微妙な色味の調整が可能です。特に赤みを強くすると暖かみのある菖蒲色になり、黄色を多めにすると落ち着いた色合いになります。
また、赤と黄色の混色の比率を変えることで、微妙な色の変化をつけることができるため、試し塗りをしながら細かく調整していくといいでしょう。
さらに、オレンジ系の色を作る際に使用する赤や黄色の種類によっても仕上がりが変わるため、いくつかの組み合わせを試してみるのがおすすめです。
青紫の色合いの作成方法
青紫自体を作るには、青と赤を混ぜることが基本です。青を主体に赤を少しずつ加えることで、菖蒲色のベースを作りやすくなります。
ただし、赤の量が多すぎると紫に寄りすぎてしまい、青の量が多いと寒色系の印象が強くなるため、バランスを見ながら調整することが重要です。さらに、青と赤の組み合わせによっても発色が異なるため、同じ比率で混ぜても使用する絵の具の種類によっては異なる青紫が得られることがあります。
そのため、複数の青や赤を用意して、最も適した青紫を作るための試行錯誤を行うとよいでしょう。
具体的な配合比率

色を混ぜる際には、それぞれの比率を慎重に調整することがポイントです。ここでは、菖蒲色を作るための最適な配合比率について紹介します。
青紫と黄色の比率
基本の割合は青紫:黄色=10:1程度が目安です。
ただし、黄色を増やしすぎると緑寄りになってしまうため、少量ずつ加えながら調整します。
また、黄色の種類によっても仕上がりが変わるため、明るい黄色と、深みのある黄色では、発色に違いが出る点にも注意しましょう。
黄色を加える際は、筆の先でわずかに混ぜる程度から始め、少しずつ希望の色に近づけていくことをおすすめします。
赤と黄色のバランス
赤と黄色の混合比率は1:1または2:1の比率でオレンジ系を作り、それを青紫に少しずつ加えることで、微妙な菖蒲色のニュアンスを出せます。
また、赤の種類によっても色味が変わるため、カーマインやマゼンタのような鮮やかな赤と、バーントシェンナのようなくすんだ赤では、最終的な菖蒲色の印象が異なります。
さらに、黄色と赤を混ぜる際には、色を均等に混ぜるのではなく、少しずつ塗り重ねながら調整することで、より自然な発色が得られます。
絵の具の種類と特性
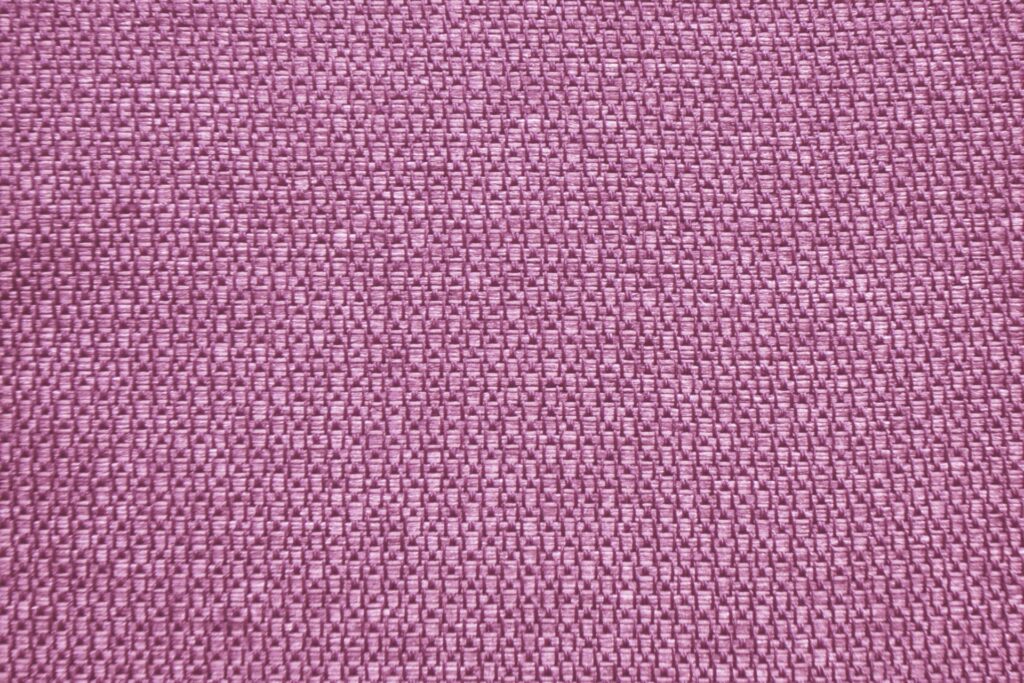
絵の具の種類によって、同じ色でも発色や混色の仕方が異なります。水彩、油絵、アクリル絵の具の特性を理解して、最適な方法を選びましょう。
水彩絵の具の特徴
水彩絵の具では、水の量を調整することで透明感のある菖蒲色を作ることができます。色の重なりを意識しながら調整すると、美しい発色が得られます。
また、水彩の特性を活かして、紙の吸収力を利用しながら微妙なグラデーションをつけることも可能です。乾燥すると若干色が薄くなるため、思い通りの菖蒲色を得るためには、少し濃いめに塗るのがコツです。
油絵の具との違い
油絵の具では、混色すると発色がややくすむ傾向があります。そのため、できるだけ鮮やかな青紫をベースに使い、慎重に色を足していくのがポイントです。
油絵の具は乾燥が遅いため、グラデーションをつけたり、色をなじませたりする時間が長く取れる利点があります。しかし、絵の具同士が混ざりすぎると、意図しない色味になってしまうこともあるため、層を重ねるようにして少しずつ調整すると良いでしょう。
アクリル絵の具の活用法
アクリル絵の具は発色が強く、乾燥後の色変化が少ないため、菖蒲色を安定して作りやすい特徴があります。筆やパレットの上で直接混ぜるのも効果的です。
また、アクリル絵の具は速乾性が高く、短時間で重ね塗りができるため、微調整がしやすい利点があります。さらに、乾燥後にツヤを出したり、マットな質感に仕上げたりと、仕上げの調整もしやすいため、多くの場面で活用できます。
色の明度と彩度の調整

菖蒲色の明るさや鮮やかさを調整することで、表現の幅が広がります。明度や彩度を変えるためのテクニックを紹介します。
明度を変更する方法
明るさを調整するには、白を少量加えると良いでしょう。ただし、白を入れすぎると菖蒲色の印象が薄れるため、少しずつ調整します。
また、白だけでなく、ほんの少しの水色を加えることで、より自然な明るさを持たせることができます。明度を調整する際は、照明の影響も考慮し、自然光と室内光の下で見比べると、実際の仕上がりが確認しやすくなります。
彩度を操作するテクニック
彩度を下げるには、グレーや補色となる黄色を極少量加えるのが効果的です。特に、少しずつグレーを混ぜることで、くすみのある落ち着いた菖蒲色を表現できます。
一方で、鮮やかにする場合は、基本色の青紫を少し足して調整しますが、純粋な青紫の代わりに濃いめの青色を加えると、より深みのある彩度の高い菖蒲色が得られます。
彩度調整の際は、一度塗りで判断せず、乾燥後の色の変化を考慮して微調整するのがポイントです。
色の一覧と比較

菖蒲色と似た色や補色の関係を知ることで、より深みのある色作りが可能になります。ここでは、近似色や補色の影響について解説します。
菖蒲色と近似色の比較
菖蒲色と似た色には、藤色(ふじいろ)や紫紺(しこん)などがあります。藤色はやや明るく、紫紺はより濃く深みがあります。
これらの色の違いを理解しながら、目的に合った色合いを目指しましょう。さらに、薄い藤色を作るには白を加え、深みのある紫紺を作るには黒や濃い青を少し足すと調整しやすくなります。
補色関係とその影響
補色の関係を理解すると、色の引き締めや微調整がしやすくなります。菖蒲色の補色は黄色系統の色であり、微量加えることで色味の変化を楽しめます。
例えば、黄色の種類によっても異なり、明るいレモンイエローを加えると柔らかく爽やかな印象に、深みのあるオーカーを加えると落ち着いたニュアンスが生まれます。また、補色を使ってグレー寄りの落ち着いた菖蒲色を作ることも可能です。
色混ぜ一覧表の活用法
混色の組み合わせを一覧表にまとめておくと、次回以降も同じ色を再現しやすくなります。記録を取りながら試すのがおすすめです。
例えば、使用する色の種類と混色比率を記録しておくことで、再現性が向上します。さらに、色見本を作成し、異なる光の下での発色の違いもチェックしておくと、より安定した菖蒲色を作ることができます。
おわりに
菖蒲色を作るには、色の組み合わせや比率、混色の試行錯誤が重要です。目的に応じた菖蒲色を見つけるために、ぜひいろいろな配合を試してみてください。


