三原色とは何か、色の仕組みをより深く学ぶことができます。
本記事では、絵の具と光の三原色の違いについて詳しく解説します。
絵の具と光の三原色とは?

三原色とは、色の基本となる3つの色のことです。私たちの目に見える色は、すべてこの三原色を組み合わせることで作り出されています。
しかし、絵の具と光では三原色の種類が異なり、それぞれ異なる混色の原理が関係しています。絵の具の場合は「減法混色」と呼ばれ、色を混ぜるほど暗くなります。
一方、光の三原色は「加法混色」といい、光を重ねることで明るくなり、最終的に白に近づきます。この違いを理解することは、アートやデザインだけでなく、印刷やデジタルメディアなどさまざまな分野で役立ちます。
また、三原色を知ることで、私たちの周囲にある色がどのように作られているのかをより深く理解することができるのです。
絵の具の三原色とは?(減法混色)
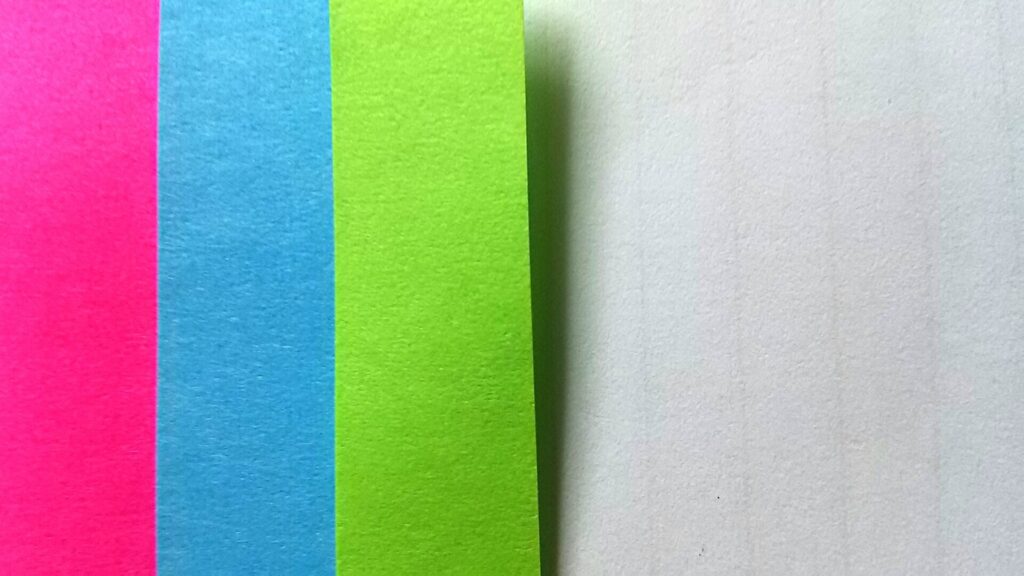
絵の具の三原色は「減法混色」と呼ばれる方法で混ぜ合わされます。この原理を知ることで、より鮮やかで意図した色を作ることが可能になります。
絵の具の三原色(シアン・マゼンタ・イエロー)とは?
絵の具の三原色は、シアン(C)・マゼンタ(M)・イエロー(Y) です。これらの色は、混ぜ合わせることで様々な色を生み出す基本となるものです。シアンは青みがかった色、マゼンタは赤紫に近い色、イエローは明るい黄色で、これらの色を組み合わせることで二次色やそれ以上の多くの色を作り出すことが可能です。
例えば、シアンとマゼンタを混ぜると鮮やかな青、マゼンタとイエローを混ぜると深い赤、イエローとシアンを混ぜると緑になります。これらの基本色を理解することで、絵の具を使った色の表現の幅が大きく広がります。
減法混色のしくみ(色を混ぜると暗くなる理由)
減法混色とは、絵の具やインクのように色を混ぜることで光を吸収し、暗い色になる仕組みです。例えば、シアンとマゼンタを混ぜると青に近い色になり、シアンとイエローを混ぜると緑、マゼンタとイエローを混ぜると赤になります。これらの組み合わせによって、基本的な色のバリエーションが生まれます。
また、すべての三原色を混ぜると黒に近づくのは、それぞれの色が光を吸収し合うためです。例えば、プリンターのインクもこの原理を利用しており、CMY(シアン・マゼンタ・イエロー)の組み合わせに加えてブラック(K)のインクを用いることで、より深い黒を表現できるようになっています。減法混色の特徴を理解することで、より自由自在に色を操ることが可能になります。
各色を混ぜると何色になる?(具体例付き)
- シアン + マゼンタ = 青(紫がかった深い青)
- マゼンタ + イエロー = 赤(鮮やかで暖かみのある赤)
- イエロー + シアン = 緑(鮮やかな葉のような緑)
- シアン + マゼンタ + イエロー = 黒(完全な黒にはならず、暗いグレーや茶色になることもある)
さらに、混ぜる割合を変えることで、さまざまな色を作ることができます。
- シアン多め + マゼンタ少なめ = ターコイズブルー
- マゼンタ多め + イエロー少なめ = ワインレッド
- イエロー多め + シアン少なめ = ライムグリーン
このように、三原色を活用することで、幅広い色のバリエーションを作り出すことができます。
黒ができる原理(CMY混色の特徴)
すべての三原色を混ぜると光がほとんど吸収され、黒に近い色が作られます。これは、各色が持つ光の波長が異なるため、それぞれの色が相互に補色関係を作り出し、結果として光の反射を減少させるためです。
この原理はプリンターのインクにも使われています。例えば、プリンターではCMY(シアン・マゼンタ・イエロー)のインクを使用し、それぞれの色を適切な割合で組み合わせることで多様な色を再現します。しかし、三原色だけでは完全な黒を作り出すのが難しいため、実際のプリンターではブラック(K)インクを追加して、より深い黒を表現できるようにしています。
光の三原色とは?(加法混色)

光の三原色は「加法混色」として知られ、色を混ぜることでより明るい色を作り出します。デジタルデザインや映像技術にも深く関わる重要な原理です。
光の三原色(赤・緑・青)とは?
光の三原色は、赤(R)・緑(G)・青(B) です。これらの光を組み合わせることで、多くの色を表現できます。これらは加法混色と呼ばれ、光の強さを増やすことで明るい色を作り出します。例えば、赤と緑を組み合わせると黄色になり、緑と青を組み合わせるとシアン、青と赤を組み合わせるとマゼンタになります。
すべての色を均等に加えると白になります。これは、私たちの目が光をどのように認識するかに基づいた仕組みです。デジタルディスプレイやテレビ画面など、日常の多くのテクノロジーでこの原理が応用されています。また、異なる波長の光を適切に制御することで、正確な色の再現が可能になります。
加法混色のしくみ(色を混ぜると明るくなる理由)
加法混色とは、異なる光を重ねることで明るさが増し、最終的に白に近づく仕組みです。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、緑と青を混ぜるとシアン、青と赤を混ぜるとマゼンタになります。これらの色の組み合わせをさらに調整することで、より幅広い色を作ることが可能です。
また、すべての光を重ねると白になりますが、この現象は私たちの目の視細胞が異なる波長の光をどのように認識するかに基づいています。デジタルディスプレイやプロジェクターなどの映像機器は、この加法混色の原理を活用し、RGBの3色を調整することで正確な色を再現します。
さらに、照明の設計や演出、舞台効果などの分野でも、この原理が応用されており、さまざまな場面で色を自在にコントロールするために使用されています。
各色を混ぜると何色になる?(具体例付き)
- 赤 + 緑 = 黄色(鮮やかで明るい色で、光の強さによってオレンジ寄りにも見える)
- 緑 + 青 = シアン(水色に近い爽やかな色で、特にデジタルディスプレイでは多用される)
- 青 + 赤 = マゼンタ(紫がかった赤で、ビビッドな色合いが特徴)
- 赤 + 緑 + 青 = 白(すべての光が合わさり最も明るい状態になり、デジタルデバイスの背景色としても一般的に使われる)
さらに、これらの光の組み合わせを微調整することで、さまざまな中間色を作り出すことが可能になります。例えば、赤と緑の割合を変えるとオレンジ寄りの黄色、緑と青の割合を変えるとより青緑寄りのシアンが作れます。また、明るさを調整することで、パステルカラーのような柔らかい色味にも応用できます。
白ができる原理(RGB混色の特徴)
すべての光を混ぜると、光の強さが最大になり白くなります。これは、異なる波長の光が目に入り、それぞれの光の刺激が均等に作用することで、脳が白と認識するためです。
この原理はテレビやスマホの画面にも使われており、RGB(赤・緑・青)の光を組み合わせることで多様な色を作り出し、最終的には完全な白を表現することができます。また、プロジェクターやLEDディスプレイなどでも、異なる強度の光を調整しながらこの原理を利用し、より鮮明な映像を再現する技術が応用されています。
絵の具と光の違いを比較!

色の混ぜ方には「減法混色」と「加法混色」の2種類があります。それぞれ異なる仕組みを持ち、絵の具や印刷技術、デジタルディスプレイなど、さまざまな場面で活用されています。
この項目では、それぞれの混色方法の違いや特徴を比較しながら解説します。 絵の具の三原色(減法混色)と光の三原色(加法混色)では、色の作られ方がまったく異なります。この違いを理解することで、色彩の知識が深まります。
減法混色と加法混色の違い
| 混色の種類 | 三原色 | 混ぜるとどうなる? |
|---|---|---|
| 減法混色(絵の具) | シアン・マゼンタ・イエロー | 暗くなる(黒に近づく) |
| 加法混色(光) | 赤・緑・青 | 明るくなる(白に近づく) |
実生活ではどのように使われている?
- プリンター では、CMYのインクを混ぜてさまざまな色を表現しています。
- テレビやスマホの画面 では、RGBの光を組み合わせて色を作り出しています。
まとめ
この記事では、絵の具と光の三原色の違いを学び、それぞれの仕組みや活用例について詳しく解説しました。
あらためてまとめますと、絵の具は「シアン・マゼンタ・イエロー」、光は「赤・緑・青」が三原色であり、混ぜると暗くなるか明るくなるかの違いがあります。


